人文社会学類では、幅広い領域の授業を用意していますが、それらを「自分のものにする」には社会や人間を研究するための基礎的な考え方を身につけることが必須です。
それは「覚える」のではなく、自分の「体の一部になる」ようにしっかりと身につけましょう。
公共の問題とその解決策の手がかりを考える授業です
公共政策論
世の中には個人の力だけで解決できない問題がたくさんあります。この授業では現代社会領域での学びを深め、公共政策論の基礎を学びながら現代社会が抱えている問題とその解決策の方向性を考えることを通して自ら考える力を養います。

「社会調査実習」を通じて地域の復興を支援する
社会調査実習
「社会調査実習」では、山形県内の山村集落を対象として、その暮らしぶりの歴史と現状について調査・分析し、報告書としてまとめます。受講者各自が具体的な調査テーマを設定し、実際に集落に訪れ、住民の方へインタビューを行い、データを収集します。

消費者問題の予防と解決へ法律を学ぶ
消費者法
消費者契約法、特定商取引法等の各種特別法と、私法の一般法である民法が、私たちの日常生活にどのように関わっているかを理解した上で、消費者問題の予防と解決のための法的枠組みを学んでいきます。

「少子高齢化」がもたらす社会問題について考えます
少子高齢社会論
現代日本社会においては、これまで人類が経験したことがない「少子高齢化」が進行しています。「少子高齢化」が生じた背景と今日的な特徴、少子高齢社会が直面する問題を理解し、解決のための手がかりを得るための授業です。

消費者の心を探り、企業による価値創造のパターンを学ぶ
マーケティング論
企業のマーケティング活動は、対象である市場、消費者の変化に対応して戦略を展開していくことです。消費者のニーズの変化を読み取り、最適な戦略を構築し、価値を創造するビジネスモデルについて学びます。

激動する現代に生きる企業の戦略を考える
経営戦略論
企業は経営環境の変化に応じて企業の行動を変更し、機敏に行動しなければなりません。その時々の経営条件に対応した戦略が必要になります。事業の選択と集中、競争優位性の構築などについて考えていきます。

社会調査などで必要なICT活用技能を修得
情報収集・分析
社会調査などで必要となる統計学の基礎知識とデータの扱い方について、実際にコンピュータを使って体験的に理解できるようにします。情報収集・分析の各過程でコンピュータを適切に活用するための基本的知識と技能を身につけることができます。

生活に必要なエネルギーの今後を考える
地域エネルギー論
東日本大震災の時に起きた福島第一原子力発電所の事故により、我が国のエネルギー政策には様々な問題が発生しています。そこで、身近なエネルギーがどのように生み出され、今後どのように変化していくかを考えます。

開かれた心と深い共感力を育む
平和学
平和学の対象には、戦争や内戦などの武力紛争だけではなく、貧困や差別などの人権問題も含まれます。国際社会における「平和状態」と「非平和状態」、「平和実現へ向けた方策」等について、具体的な事例を通じて考えます。

外国で暮らす少数民族の生活から共生について考えます
ディアスポラ学
外国に少数民族として暮らす居住形態をディアスポラ(離散)と言います。ディアスポラの民には、独自の文化を保ちつつホスト国とうまく折り合いをつけていく知恵があります。世界や日本で暮らす彼らの生き方から平和と共生について考えます。

本や雑誌をめぐる文化の現在についての理解を深めます
出版文化論
現在、出版を取り巻く状況は大きな転換点にあります。この授業では、本や雑誌をめぐる文化の現在について、出版産業のしくみ、書店や図書館はどのような存在か、読書の意味、電子書籍やネット書店の影響という視点から学び、理解を深めます。

人文系学問とは?その特色や魅力に迫ります
人文科学入門
人文(科)学は、人間や文化について研究する学問の総称です。この科目では、哲学、言語学、文学、史学、芸術学、文化人類学など、人文(科)学に属する学問で、どのようなことが研究されているのかについて学びます。そして、この学びを通して、2年次以降、自分がどの学問を中心に学んでいくかの手がかりとします。

人と社会との関わりについて多角度から洞察を深めます
社会学
われわれの生活する社会は、貧困・格差、災害、人口減少などさまざまな問題を抱えています。社会学は人と人とを結びつける「しくみ」に着目し、その「しくみ」からこれら問題がなぜ、どのように発生するのか、考えていきます。
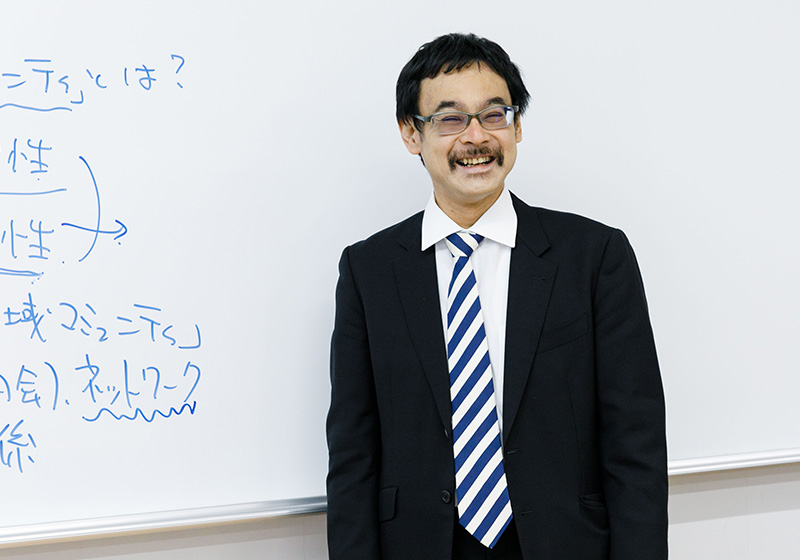
ゼミ学習で何が学べるか?大学ならではの学修について理解
人文社会演習
人文社会学類では、3・4年次のゼミ活動、そして卒業論文の執筆があります。そのために2年次の人文社会演習では、ゼミ学習とは何か、各ゼミで何を学べるのかをじっくりと理解していきます。この授業を通じて大学の専門教育に対応することができます。

異文化を学び、人間を知る。「当たり前」を疑おう!
文化人類学
文化人類学の学説史と基本的思考方法を提示します。また、日本で学生生活を送っている受講者に身近な事例と、あまりなじみのない異文化の映像などを使って人間と文化人類学への理解を深めます。

人間存在の本質とその生き方を考える
倫理学
難破した船は、繫留されるべき港を探し求めます。ただ、それがどこにあるのか分かりません。ただ波に身をゆだね、その中で舵を取らなければならないのです。自らの羅針盤を見つけること−授業を通して、ひとり一人が、この課題の答えを探していくことになります。

職業キャリアへの第一歩を踏み出す!
キャリアデザインⅠ
日本の雇用システムの特徴や雇用状況を認識した上で、職業と人生、自分の生き方について真剣に考えます。そして、卒業後の職業キャリアの目標を設定し、その実現に向けて大学生活の中でどのように学習し行動していくのかをプランニングします。
